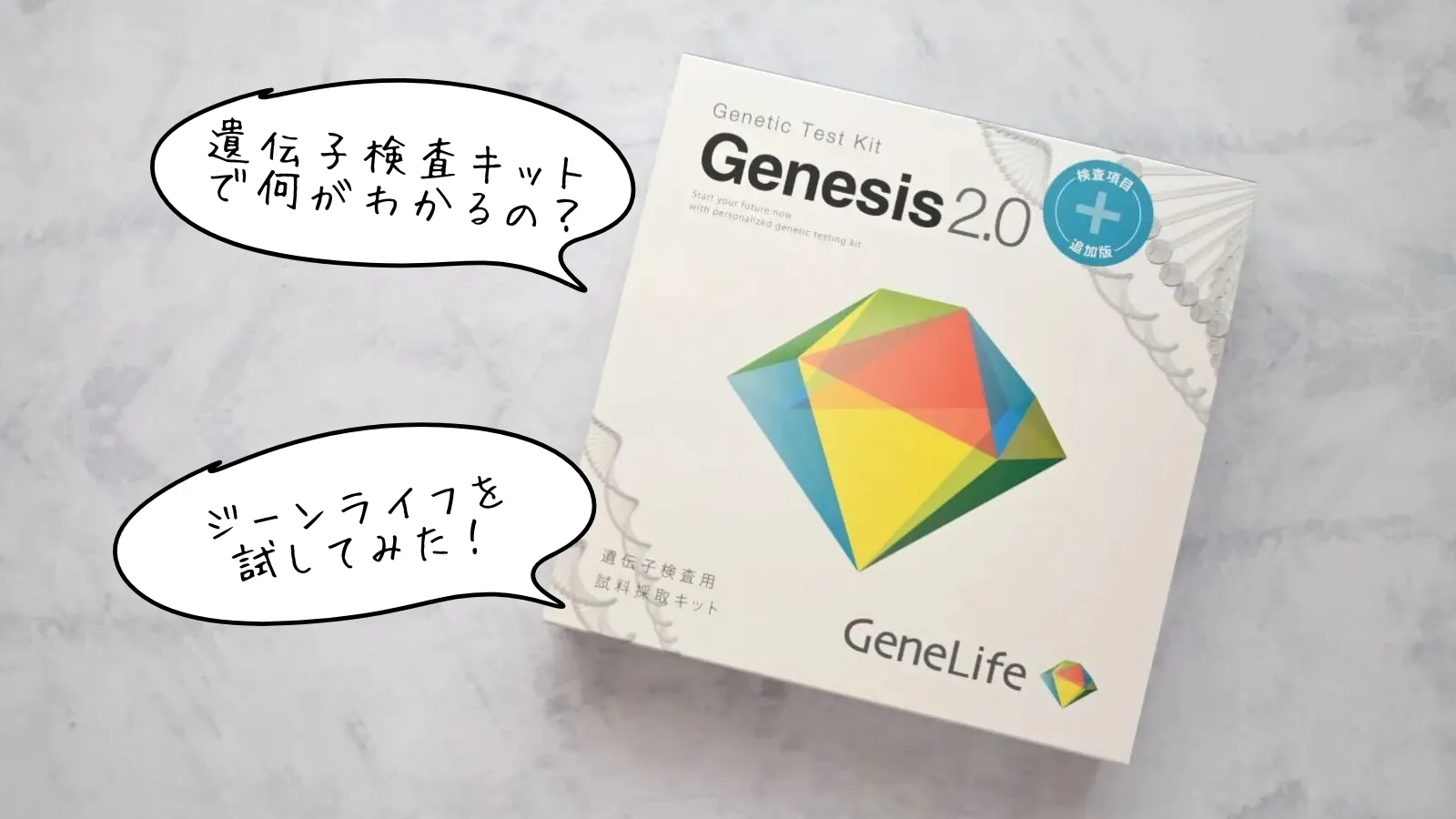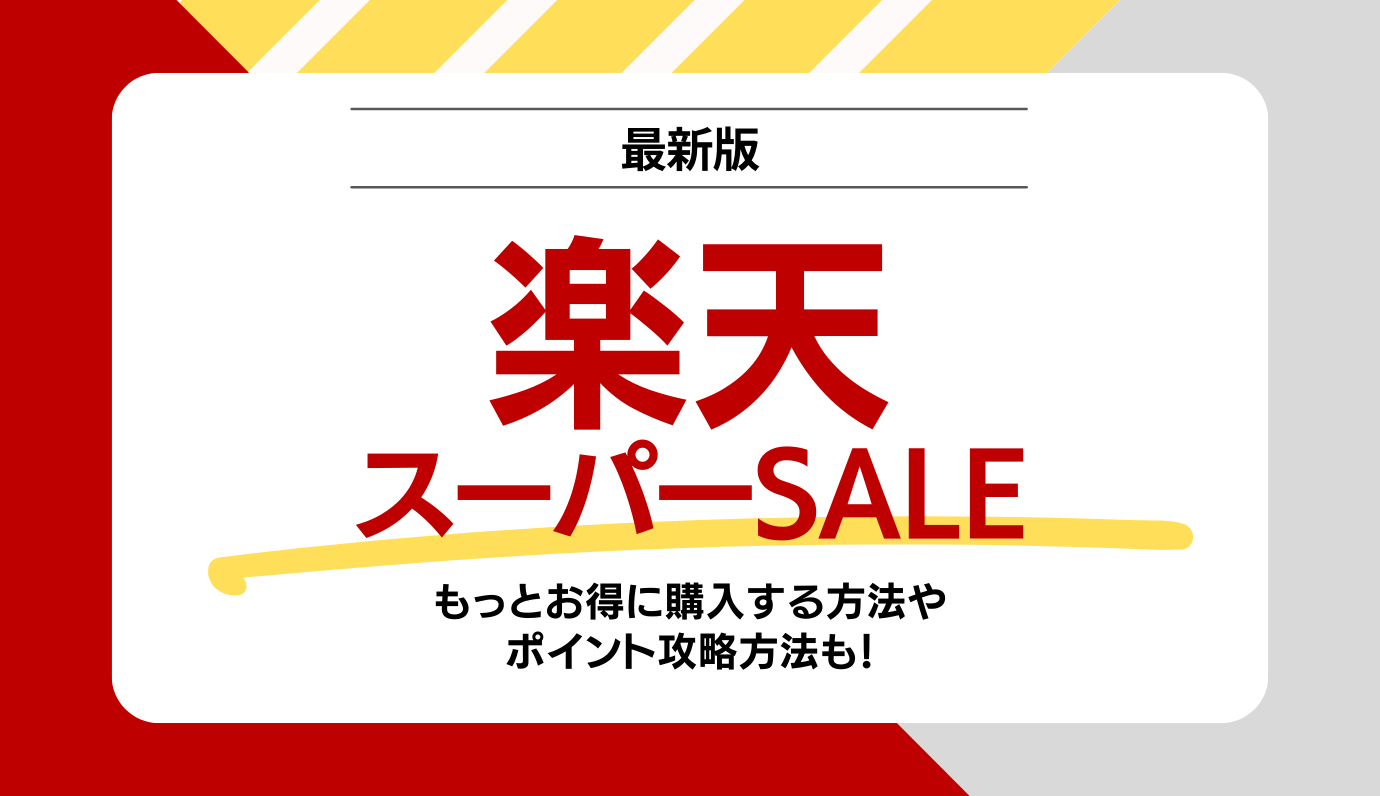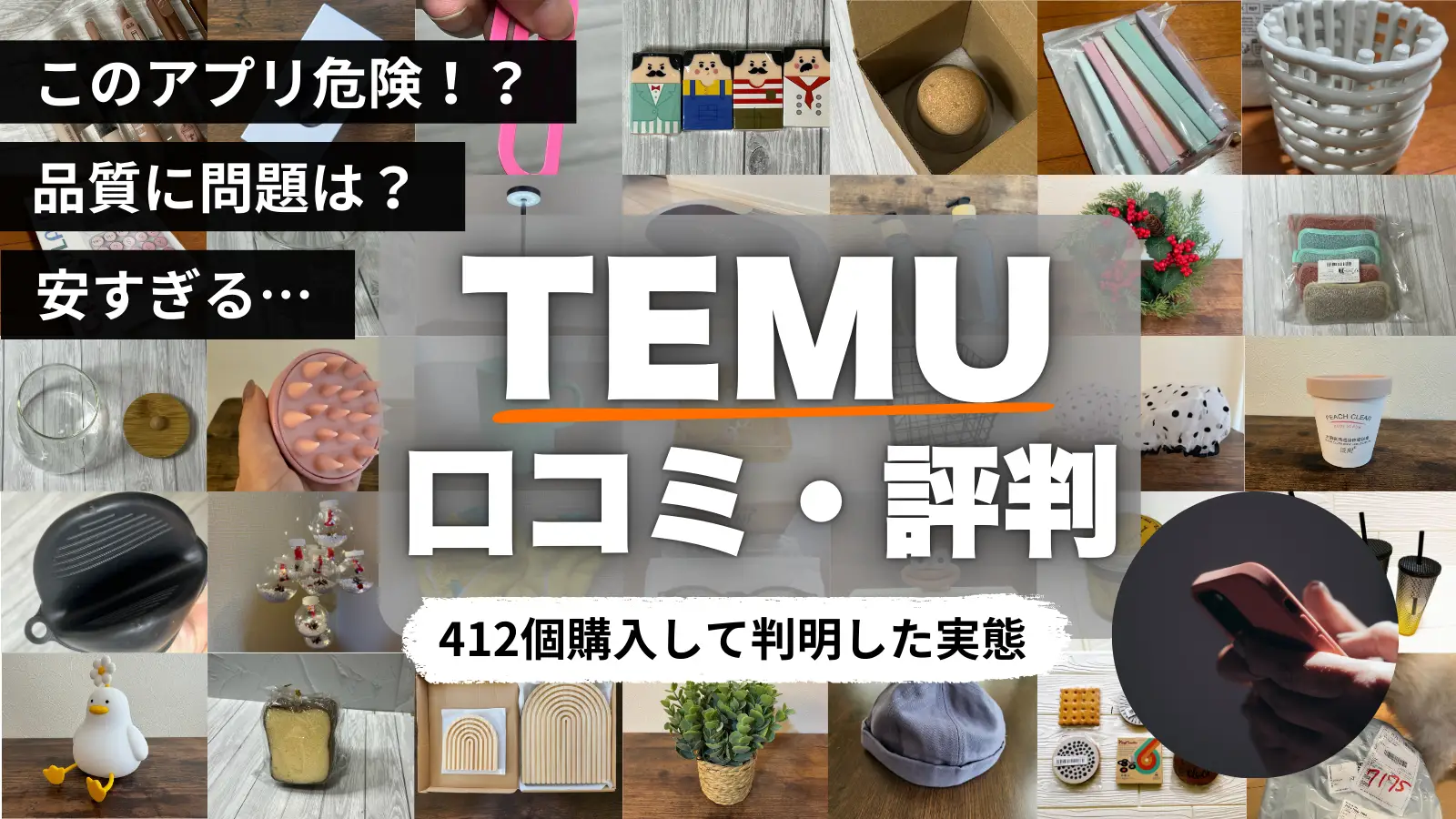子どもと一緒に考える「健康」と「環境」。ライオンが届ける新しい学びの形
ライオン株式会社は、使用済みハブラシを回収してプラスチック製品に再生する「ハブラシリサイクル」の活動を2015年から行っています。埼玉県と連携して始まった私立幼稚園・認定こども園での取り組みの一環として、2025年9月17日に双恵学園・双恵幼稚園で出張授業を実施。その様子をワタシト編集部がレポートします。
さらに、ライオン株式会社 執行役員サステナビリティ推進部長・西永英司さんをはじめ、本活動の関係者の方々に、取り組みの概要などについて話を聞きました。
紙芝居とダンスで楽しく学ぶ、歯と環境の大切さ

元気いっぱいの園児がホールに集合!ライオンの方々から、歯の役割や、使い終わったハブラシがどのようにリサイクルされるのかをテーマにした紙芝居が披露されました。合間にはクイズも出題され、園児たちは笑顔で答えながら、正解すると大喜び。会場は大いに盛り上がりました。
紙芝居には「歯みがきが私たちの健康に欠かせないこと」「古くなったハブラシはゴミではなく新しいものに生まれ変わること」といった「健康」と「環境」にまつわるメッセージが込められており、園児たちは興味深そうに耳を傾けていました。

「使い古したハブラシは、歯みがきがしづらくなります。毛先が開いてきたら、交換しましょう。そうすると、歯をきれいに磨けるようになり、元気な歯でおいしいものを食べられます」
園児たちは「うんうん」と頷きながら、真剣な表情で聞き入っていました。
さらに、食事をおいしく楽しむためには正しい姿勢が大切であることが伝えられ、その姿勢づくりに役立つ取り組みとして「おくちもからだもワクワクダンス」が紹介されました。

理学療法士が監修した「お口と体の動かし方」を学べるダンス動画が放映されると、園児たちは真剣に見たり、映像に合わせて小さく体を動かしてみたりと、思い思いに楽しんでいました。リサイクルポーズなど、ダンスの中にも環境への配慮が取り入れられています。
動画を一通り見終えたあと、実際に踊る時間に。園児たちは一生懸命、生き生きと取り組みます。
最後は「紙芝居やダンスはこれからもやってみてね」というメッセージとともにお別れの時間に。別れを惜しみ、ライオンのスタッフの後をついて行こうとする子どもたちの姿が印象的でした。楽しみながら学び、充実した時間になったようです。

この日は園内にハブラシの回収ボックスが設置されていて、子どもたちがハブラシを入れる姿も見られました。子どもたちの歯みがきへの意識を高めるだけでなく、リサイクルが身近になるきっかけにもなりそうです。

回収されたハブラシはリサイクルされ、手鏡や植木鉢、定規などに生まれ変わります。ライオン本社の社員食堂で使われている配膳用トレイも、リサイクルされたハブラシから作られているそうです。
自治体や学校と連携し広がる回収の輪

ーーハブラシリサイクルの活動について、詳しく教えてください。
西永さん:ライオンでは、口の中を清潔に保つために月1回のハブラシ交換を推奨しています。日本国内では年間約4.5億本ものハブラシが消費されています。ハブラシ製造を担うメーカーとして、使い古したハブラシがただ処分されている状況をそのままにしておくわけにはいかないと考えました。そこで始めたのが「ハブラシリサイクル」の活動です。2015年にスタートし、今年で10周年を迎えます。
ーー過去には、どのような場所で活動してきましたか。
西永さん:これまで各市区町村と連携し、役所や小学校、児童館、商業施設などでハブラシの回収を行ってきました。
東京都板橋区:約7万本
東京都台東区:約2.6万本
兵庫県明石市:約0.7万本
10年にわたる活動で、累計21.7トン(約216.8万本)ものハブラシを回収・リサイクルしています。
ーー今回は、なぜ双恵学園・双恵幼稚園と共同で取り組みを行ったのでしょうか。
西永さん:ライオンと埼玉県で「ハブラシリサイクル」の展開を検討する中で、全埼玉私立幼稚園連合会をご紹介いただきました。同連合会が子どもへの環境教育に力を入れていることから、その一環として今回の開催に至りました。埼玉県と共同で行うのは今回が初めての試みになります。2025年度は埼玉県内の10園で0.4トン、2027年には540園で30トンの回収を目指しています。
今井さん:また、今回のイベントに先立ちPTA総会で保護者向けのプログラムを実施した際には、700本ものハブラシが回収され、保護者の方々の関心の高さを実感しました。そうした成果を踏まえ、松尾園長にご協力をお願いしました。
ーー実際に取り組んでみていかがですか。
松尾さん:想像以上に子どもたちが楽しそうに参加してくれましたね。紙芝居やダンスを通じて、子どもたちが実体験を交えながら環境について学べたのは、とても有意義でした。双恵学園は就学前の子どもたちを育てる場であり、彼らは20年後、30年後に社会を担う存在です。その未来のために、今の大人たちが環境をより良くする努力を重ねる必要があると思っています。
今日ご覧いただいたように、子どもたちは驚くほど柔軟に学びを吸収します。この大切な時期に環境について伝えることが重要だと思いますし、こうした取り組みが今後さらに広がっていくことを期待しています。
ーー埼玉県として、本取り組みをする意義はどこにありますか。
石田さん:サーキュラーエコノミーという言葉や考え方は、まだ十分に普及しているとはいえません。環境への関心は高まっていますが、浸透はこれからです。だからこそ、吸収力の高い子どもたちに学んでもらい、そこからご家族に伝えてもらえるといいですね。

ーーリサイクルしたものは、どのように使用していますか?
西永さん:回収したハブラシは再生してペレットにしたあとで、定規や手鏡、植木鉢などに作り替えてイベントなどで活用しています。実際に手に取ることで、子どもたちにリサイクルを実感してもらえると思います。手鏡を配布するとお母様たちが「ハブラシがこんなふうに生まれ変わるんですね」と喜んでくれます。
◇◇◇
今回の楽しく学べる取り組みは、園児たちが健康と環境について考えるきっかけとなったのではないでしょうか。同園では今後も回収ボックスを設置し、動画やダンスを先生方に覚えてもらい、継続的に活動が行われていくそうです。私たち大人も、ハブラシを交換して健康を保ちながら、古くなったものはリサイクルするという発想を持っていきたいですね。
取材、文/ゆう
ワタシトJOURNAL特集ページはこちら
.jpg)
※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。